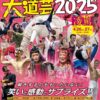平田オリザの仕事 Work of Oriza Hirata
演出のような前書き
青年団という間の抜けた劇団名で芝居を続けて10年以上になる。
まあ、最近つくづく「こんなことになるとは思わなかった」と考える。
あらゆることに関して……。
ここに書かれた演劇論は、すべて私たちの劇団の稽古場の中から生まれてきたものだ。
決して理論や予測が先にあって私たちの演劇が生まれてきたのではない。
例えば青年団では役者が完全に後ろを向いて喋ることがよくある。
「客に尻を向けない」という従来の演劇の鉄則はここでは完全に無視される。
この最新·最前衛(?)の演劇スタイルは、実はいまは劇団を辞めて某市の現代美術館で学芸員をしているSというとてもわがままな女優が「こんな普通の台詞をお客の方を向いて喋るなんて恥ずかしい」と言って後ろを向いてしまったのがその始まりだった。
私は何だか変だと思っていたのだが、見ているうちにどうもそちらの方が都合がいい。
「後ろを向いた役者の背中に前からの照明を一切あてずに影を作る。
その影越しに対話者の表情を見せることによって、よりいっそうの遠近感を出すことが可能になる」といった理屈は、すべて私があとから苦し紛れに考えたものだ。
理論なんてそんなものだ。
しかし、ここに展開される理論が私たちの活動を支えてくれた事実も否めない。
この理論があったからこそ、私たちは自らの演劇を信じて、また新しい演劇の可能性を信じて舞台を創ってこられたのだと思う。
先日ある新聞の演劇担当記者から、「あんたは何でそんなに自分のやってることに自信が持てるんだ?」と聞かれた。
自信なげにインタビューに答えたら誰も記事にしてくれないし誰も芝居を見に来てくれないじゃないかという正論は心の内にしまっておいて、私たちのやっていることには、論理性があるからです」と私は答えた。
するとその記者は軽く、「いや、だって芝居は論理じゃないでしょう」と一言う。
私は内心しめたと思ったが、その思いはやはり隠して、次のように答えた。
「どうして、演劇をしてもいないあなたが、『演劇は論理ではない』などと言えるのか。そうではないのだ。
『演劇は論理ではない』と軽々しく一言える日本の演劇の構造自体が問題なのだ。
『演劇は論理じゃない』というのだって、それは立派な演劇論じゃないか。
その自己撞着にさえ気がつかない演劇は、二一世紀に生き残れないと思いますよ」
私はいま、ここに堂々と宣言したいと思う。
私たち青年団の演劇は論理に支えられていると。
そして、その論理「現代口語演劇理論」は、単なる演技論·演劇論ではなく、人間と世界の見方を示すある一つの普遍性をもったものだと。
さて、この本は、あまり関係のないような事柄が、ボコボコとかなり乱暴に、少々読みやすさを無視しながら並べられている。
だからみなさんには、目次を見ていただいて、できるだけ自分に興味のある項目から読んでいただければと思う。
文章自体はできるだけ読みやすく書いたつもりだ。
最初の大きな論文の中に出てくる言葉のこと、日本語のことなどから入るのもいいかもしれない。
実際、講演などで喋るときにはこの話題から入ることが多い。
いずれにしろ、この本を読み終わったあとに、まさにそのとおりと膝を打つ人より、何だかちょっとだまされてるんじゃないかと思ってくれる人の方が多いと思う。
そこにおそらく、私の考える演劇と、すべての議論はそこから始まる。
すべての物語は、ここから始まる。
あなたの考える演劇との差異が浮かび上がる。


1、演劇は可能か
演劇は可能か?
可能であるとすれば、それはいかなる演劇か?
私はそのことを考える。そうして仮に「演劇は可能だ」という命題を立ててみる。
これから記す事柄は、すべてその仮の命題に拠って立っている。
もし演劇が可能だとするならば、私にとっての演劇は、少なくとも以下のような要件を備えていなければならないだろう。
-演劇とは何か
劇は一般に、作る側と観る側との関係性を要求する。
音のない演奏というものが想定しにくいように、役者のいない舞台、観客のいない公演というものも、現在のところなかなか想定しにくい。
グロトフスキーもピーターブルックも鈴木忠志氏も、みな「演劇は、どこかの場所で、観客と俳優の間で起こるもの」と定義している。
これはいずれも、さまざまな添加物にまみれた「近代演劇」を否定する文脈で語られた言葉であり、現在のところ「演劇とは何かという問いに対するもっとも正統的な答えだと考えてもいいだろう。
二十世紀後半の演劇は、俳優中心の演劇であった。
実質、注目を集めたのは演出家個人であったが、しかしそれらの演出家はみな, 「俳優の復権」を唱え、「俳優のテキスト(=物語)からの解放」を主張した。
それは、いわゆる近代演劇が、(この文章の中でもすぐあとに考察するが)イデオロギーを伝達するための道具として使われ、そのために戯曲中心主義、作家中心主義に陥ってしまったことへの当然の批判であった。
だが、今日、エンターテイメントの分野から前衛芸術の分野にいたるまで、例えば「機械だけの演劇」が普通に見られるようになってきている。
グロトフスキーは「人形芝居のうしろには俳優がいる」と言っているが、しかし、コンピューターで動く機械のうしろには誰も存在しない。
そこにはコンピューターをプログラミングした劇作家·演出家がいるだけだ。
作家、演出家の区分については,またこれもあとで詳しく述べるが、いまは一応、この職分をまとめて劇の作り手としておこう。
「機穢だけの演劇」には、劇の作り手はたしかに存在するが、俳優は存在しない。
このことを、単なる技術の進歩による状況の変化とだけ受けとめるのは間違いだと私は
考える。
オランダのメスダッハ市に「パノラマ·メスダッハ」という娯楽施設がある。
一九世紀に造られたこの建物は、地下の通路を通って建物の中央部にしつらえられた東屋に出ると周囲にオランダの海岸の風景が広がって見えるようにできている。
東屋の周囲は本物の砂が敷き詰められている。
遠い風景は絵画なのだが、これが遠近法を巧みに利用して実物の砂との境目をごまかすように作られているのだ。
観客は一瞬、自分が本当に海辺に来たような錯覚に陥る。
そのあとは、それが巧妙なだまし絵であることを思い出し、さまざまな細部の工夫を見て回るわけだ。
こういった巨大なパノラマは、映画が出現する以前に大変な流行を見せた。
空間的なパノラマから小さな覗きからくりなども含めて、これらの体感的な展示物は、つねに一九世紀の博覧会の目玉であった。
この パノラマ·メスダッハ」を私はたいへん演劇的だと感じるのだが、いかがだろうか。少なくとも、この作者の意図は、私の演劇の目指す方向とたいへん近いように思うのだ。そうなると、私が考える演劇は、「観客と俳優の間で起こるもの」という先ほどの定義からは、いささか外れていくことになるようだ。
そこで私たちは、議論をもう少し先へと進める必要があるのではないだろうか。
仮に私は演劇を、次のように定義して論議を進めようと思う。
演劇とは、ある場所で、観客の目の前で、作り手の作為がもたらす何らかの出来事である。
こう書くと、「いやパノラマは演劇ではなく美術だろう」という反論が当然予想される。
通常、美術と演劇を分ける重要なポイントは、演劇の一回性という点だろう。
演劇はまったく同じものを繰り返すことはできないとされてきた。
しかし私は、この一回性というやつは食わせものだと思っている。
ここには、二〇世紀ヒューマニズムの罠が見えかくれするからだ。
このことも、あとで俳優について述べる段でさらに詳しく語ることになるだろう。
いまはともかく先を急ごう。
ここではただ、美術作品との相違とされてきた事柄についてのみ考えてみよう。
美術作品はたしかにたいてい持ち運びが自由で、同じものをどこでも鑑賞できる。
しかし、いま私たちが問題にしているのは、作り手と受け取り手の間に起こる出来事についてであった。
これを作り手と受け手の関係と言い換えてもいいだろう。
そうなってくると、美術作品もまた、ある一枚の絵が、ある人間の前に現れる瞬間という現象面を捉えるなら、充分に演劇であるといえるだろう。
例えば、もっと単純な話、繰り返し消費される商業演劇がその一回性を根拠に演劇と呼ばれ、パノラマ·メスダッハが美術と呼ばれるのは私には納得ができない。
現実に即して考えてみても、1枚の絵は単なる美術作品かもしれないが、建築家によって意図された美術館に優れた学芸員によって配置された絵画の展示とそれを見に来る観客の関係は、もはや演劇と呼んでもいいのではないかと私は思う。
これはもちろん、私が美術家ではなく演劇人だからだろうが、だから逆に演劇も美術なのだといってもいい。
そんな定義付けはどうでもいい。
もはや、そのレベルで引かれる境界線に意味はないということだ。
また、関係ということに注目するならば、それはもはや、美術品のような具体的な事物である必要すらない。
手紙の交換、のろしを上げることなども立派な演劇となりうるだろう。
それはおそらく、そこで私たちは、さらにもう一つ論議を進めることができるだろう。
次のような命題になる。
演劇とは、ある場所もしくはある時間に、観客と作り手の間に、作り手の作為によってもたらされる何らかの出来事(関係)のうち、自らを演劇と規定するすべての出来事(関係)である。
自らを演劇と規定するものをすべて演劇と呼んでしまうのでは、これは演劇とは何かという考察を放棄してしまっているように思われるかもしれないが、私はこれから始める長い議論の出発点としては、これで充分であると考えている。
私たち演劇に実際携わる者たちは、自分たちの存在証明を得るために、とかく演劇をたいそうなもの、他の分野と異なったものとしてしまう癖がある。
しかし、演劇を演劇たらしめている要素など実は何一つないのだ。
演劇とは何かを規定することは、その瞬間に演劇を物神化することだといってもいい。
演劇とは何かを規定することは意味がない。
しかし演劇はある。
こうして私は、演劇に至るすべての梯子を外したうえで、もう一度演劇について考えてみたいと思う。
演劇とは何だろうか。
私の演劇とは何だろうか。
2 演劇の嘘
人は、演劇を始めるに際して、普通、次のように考える。
さぁ、とにかく、舞台の上では何かをしなければならない。
もちろん,この舞台とは従来の「劇場」という空間だけを指すのではない。
ある時間、ある空間をここでは便宜上、「舞台」と呼んで論議を進める。
舞台の上で何かをする者がいる。
コップ1つ置いたとしても、そこにはコップを置いた者の作為がある。
そして、それを見る者が, そこに演劇が成り立つ。
演劇は作り手の作為を前提とする。
だがしかし、ここに演劇の危機の本質がある。
舞台には何らかの作為が必要だ。
それはまぁ確かなことなのだが,だがしかし、何かをやるとみなそれが嘘にしか見えなくなってしまう。
ここに現代芸術の抱える共通の問題点がある。
これは、現実感の喪失の問題といってもいいだろう。
この問題は、現代芸術共通の問題ではあるが、特に演劇には「嘘」が貼りついているように思える。
ここで私がいう とは、信じられないもの」「現実感のないもの」そして同時代性のな
いもの」と考えてもらいたい。
さて、では何故、演劇には特にこの「嘘」がつきまとうのだろう。
逆説的に聞こえてしまうことを恐れずに言えば、それはおそらく演劇が、三次的な記号である文字や絵の具を通さない、非常に直接的な表現手段だからだ。
演劇はこれはで主に一次的な記号、肉体と肉声によって成り立ってきた。
二次的な記号に支えられた小説や絵画は、一般の人々にとっては嘘がある程度前提となっているらしい(もちろん、詩をはじめとして、この分野とて危機に瀕してはいるが)。
しかし、生身の身体が演ずる演劇は、どうもそうはいかないようだ。
ちょっと苦しい説明かもしれないが、「絵のような」「詩のような」という形容と「芝居がかった」という言葉の与えるイメージの違いを考えてみてはどうだろうか。
「絵のような1%のような」は何だか浮ついた感じだが、あまり悪意が感じられない。
三次元を二次元に閉じこめてしまった絵はもともとがフィクションで、だからこれを嘘という人はいない。
ところが、「芝居がかった」というのは何となく悪意があって、「本当」をやらなくてはならないのに「嘘」をしているというイメージだ。
演劇も、もちろんフィクションなのだが、これが「フィクションです、何をやってもいいんです」と開き直れないのはどうしてだろう。
ここで私は、もう一度、先の演劇に関する命題に立ち帰ってみる必要があるようだ。
「演劇とは、ある場所もしくはある時間に、観客と作り手の間に起こる出来事(関係)だ」と私は考えたのだった。
とすればそこには、フィクションではすまされない関係、たしかにそこに何事かが起こったと観客と作り手が相互に確認しあえる関係が、観客の側から「いま」「この場で」要求されていると考えるのが妥当なのではないだろうか。
そしてそのような関係を、人々は演劇的と呼んできたのではなかったか? 人がある演劇を積極 的に受け入れるのは、そのような関係を切り結んだときではなかったか?
しかし、では、このような関係ははたして可能だろうか?
私たち近代人は、すでにコップを置いた者の作為を知っている。
物理的に机の上にコップを置いたのはAという役者だが、しかし本当に机の上にコップを置いたのは彼だろうか、戯曲家だろうか、演出家だろうか。
私たちはコップを置かせた背景にある意図を読みとる。
それは共産主義思想であったり、国粋主義であったり、青春の甘い恋心であったりするのだが、すでに観客はその作為の匂いを嗅ぎつけ、俳優の次の動作を予測し、さらに結末と主題を吟味して演劇を理解する。
徹底的に理解する。
ここには、「いま」「この場で」という関係はない。
だからここには、出来事はない。
伝達があるだけだ。
意味の伝達、主義主張のプロパガンダがあるだけだ。
では、このような状況で、出来事と呼びうる確かな関係を築く可能性はあるのだろうか。私はしっかりと「ある」と答えようと思う。
ただそのためには、もう少し回り道をしていかなくてはならない。
3 近代思想とリアリズム
近代の芸術の歴史は、主観からの逃走の歴史であったといってもいいだろう。
芸術が特権階級のものから一般の近代市民のものへと移行する中で、限られた者のための約束ごとから、より大きな普遍性を持った約束ごとへと、芸術はリアリズムへの道をひた走った。
ここでいうリアリズムとは、単純に先ほどの嘘という概念の逆方向,より信じられるもの」「より現実感のあるもの」「より同時代性のあるもの」へと進む方向と考えてほしい。
よりリアルな感触を求めるのは、ロマン主義·形式主義と並んで、芸術表現の根幹をなす二大潮流といっていいかもしれないが、それが近代において加速されたのは事実だろう。
この「リアルなものへの傾斜の加速には、近代思想が大きな役割を果たしていると私は考えている。
ここで私がいう「近代思想」とは、社会の本質や人間存在の意義などは、人間の理性に
よって正しく認識されうるのだという考え方である。
「正しく」とは、客観的にという意味である。
近代思想では、この「客観性」という言葉が重要視される。
ここで議論をわかりやすくするために、近代思想が想定した主観と客観の相違を、次のような系列で示してみよう。
主観の系列(前近代) 作為→主観→(神などの前近代的な真理)
客観の系列(近代) 客観→リアル→真理
ここではまず「作為」と「真理」が対立項とならずにずれていることを記憶しておいてほしい。
さて、このリアルなものへの傾斜と近代思想の関係のもっとも完璧な例が、いわゆる社会主義リアリズムだ。
近代思想の中心をなす認識論を突き詰めていけば、人間の合理的理性は社会を正しく把握し、さらにその把握に基づいて、社会を理性によって変革、管理しうることになる。
そこから生まれる論理展開はやがて、「現在のこの世界は、このように悲惨であるが、しかし人間は合理的理性によって社会を変革し、別の理想的な社会を作り出すことができる」という結論に達する。
このような思想を背景とした社会主義リアリズムは、以下のような方法論をとる。
現在の社会はこのように悲惨であるが、その悲惨さは科学的に分析可能であるから、芸
術家はその分析の再現に専心すればよい。
また、このような悲惨な社会は、しかし合理的理性によって、共産主義社会へと変革できるのであるから、芸術家はその変革の筋道と達成された理想社会や理想的人間像の描写にも専心しなければならない。
ここでは、いささか極端に社会主義リアリズムを揶揄してしまったが、近代思想と密接な関係を持つ近代芸術の多くは、このような社会主義リアリズムとほとんど同じ構造を持っている。
簡単に言い換えてしまえば、それは、主義主張の伝達、イデオロギーの伝播に奉仕する芸術だ。
この主義主張のための芸術は、実は現在でも表現の主流をなしている。
それは革命思想の流布といった明確な形をとらなくなっただけで、現在流通しているほとんどすべての演劇が、商業演劇から前衛演劇に至るまで、作り手の何らかの道徳観、価値観を観客に示そうと意図されている。
しかし、現代社会と現代人は、このような近代主義の限界を無意識のうちに知ってしまっている。
人間は、社会や世界や人間自身を正確に把握することはできない。
現在の社会を正確に把握できないのであるから、もちろん理想の社会像を描き出すことなどできないし、また理想の社会は決して到来しない。
絶対的真理は存在しないか、もしくは存在するとしてもそれを人間は認識することができない。私たちは以上のことをすでに漠然と知ってしまっている。
では、芸術は、演劇は何を伝えればいいのだろうか? 私は何も伝えるべきものなどないの
だと思う。
ただ演劇は、人間を、世界を直接的に描くことができればそれでいい。
真善美といった価値基準や道徳からいったん離れて、現実世界を直接的に把握する手段を私は芸術と呼ぼうと思う。
これは一見、「人間は人間を正確に把握することはできない」という先の命題に矛盾するようだが、そうではない。
人間は人間を正確に把握することはできない。
しかし、だからこそ、この価値観の混乱状態において芸術家は、その天分を傾注して「私はこのように世界を把握する」という一つの個的な認識の典型を示していかなければならないのではないか。
それが、多くの変遷を経ながら古来より変わることのない芸術の本質なのではないか。
例えば何か凶悪犯罪が起こったとする。
私たち芸術家がなすべきことは、評論家のようにそのことの善悪を説くのではなく、その事件の本質を直接的に捕まえ描写することだ。
真善美といった価値観の混乱が起こっている現代社会にこそ、この価値観から一歩身を離し、事態の本質に迫る芸術が必要とされているのではないか。
4 芸術の必然
さて、では、その価値観の混乱とはいったいどういうことだろう。
例えばここに、いくつかの命題を並べてみる。
a、人を殺してもいい/いけない
b、日本は核武装すべきだ/すべきでない
c、女子高生はブルセラショップで下着を売ってもいい/いけない
d、女子高生の靴下は無地でなくてはいけない/ワンポイントまで/どうでもいい
e、エイズ感染者は日本に入国させない/させてもいい
とまぁ、こういったことを列挙して、かつてならば、ある一定の社会階層や思想区分によって、その解答は一定のものとなった。
封建主義共産主義といった秩序だった思想体系の中では、これらの命題は一元化され、社会全体がある一定の解答を持っていた。
ところが、いまはどうだろうか。
「人を殺してはいけない」という命題とr靴下の模様はワンポイントまで」という命題を、同じ規則」として教え込まれる高校生に、さて本当に人を殺してはいけないと判断させることができるだろうか。
私は少なくとも、「隣町の高校では、靴下の模様は自由だから、隣町では人を殺してもいい」という高校生が多数出現してもさほどおかしくはない状況に、現代の日本はおかれていると考えている。
だがしかし、私たちは、というより優秀で健全な高校生たちはこっそりと靴下に模様を入れても、こっそりと人を殺したりはしない。
私たちは、この混沌とした日常の生活において、そのように常に世界を把握し、判断を下し続けることによって、人生の時間を1歩1歩先へと進めている。
またその判断は個人にとどまらず、ある種の価値や感動を共有し、私たちは共同の生活を営んでいる。
ただ,もちろん一般の人々はそのことに気づいてはいない。
ここに芸術の必然がある。
芸術作品を見て人が感動をするのは、突き詰めていえば、「あぁ、たしかに私は,世界をこのように認識している」という感覚が起点となるのではないだろうか。
そして、ここに私は、出来事と呼びうる確かな関係の可能性があると考える。
このことはまた、他者の理解に関しても同様のことがいえるだろう。
「あぁ、彼は,このよう、自らの世界認識の意識化を助け、別の種類の感動を呼ぶこともあるだろう。これを延長して考えれば、異文化の理解に芸術がいかに役立つかを説明すに世界を認識するのか」という感覚がるのは容易なことだ。
いささか走りすぎたが、ともかくも私は主義主張の演劇を否定し,世界をダイレクトに描写
する演劇を目指したいと思えこのことは現代を生きる芸術家の使命であると考えるし、またそのようなことが、これまで幾度も試みられてきた。
しかしながら、現代演劇と呼ばれるジャンルが、とりわけ日本の現代演劇が、はたしてそのような変貌を遂げ、近代思想の呪縛から解き放たれたかといえば、そこらへんのところはまったくもって心許ない。
では、この現代演劇の停滞は、
どういった理由から来たのだろう。
5 演劇と映像
例えば、土門拳は、リアリズムについて次のように述べている。
絵の技術が進んで精巧に描ける様になった時、絵が高度に発展した時、なぜ写真が発明
されたか、それは絵がどんなに精巧であっても主観を通じて描くから、そこには必ず嘘が
あるからだ。
あくまでも現実を現実として見る場合、コップは神が造ったものではなくてわれわれが造ったものだ、子供は、神様からの授かりものではなくてわれわれが造ったものだと考える様になった。そして科学が非常に進歩してきた。この時リアリズムの要求で写真が生まれた。
私がいまここで進める論議では、先ほどの系列表にしたがって、主観=作為と考えてもらっていい。
そしてどうもこの一連の概念には、嘘がつきまとってくるようだ。
だが、と私は考える。
絵が発展して写真が発明された。
では演劇が発展して映画が発明されたのか?
私はそうは思わない。
そしてここらへんに二〇世紀の演劇の大きな誤りがあったのではないかと私は考える。
絵はどこきいっても紙と絵の具で、写真ではそれが印画紙に変わった。
対象への主観性が少なくなった分、少なくとも単純な意味でのリアリティは増すわけで、これは土門拳のいうとおりだ。
ところが演劇の場合はどうだろう。
演劇はもともと、物や人が舞台の上に在るわけだが、映画はそれをスクリーンに閉じこめてしまった。
リアリティの問題からいえば、これは後退に他ならない。
写真が発展して映画になったというのなら話はわかるが、演劇が発展して映画になったということはできないだろう。
もっと簡単な説明を試みれば、例えば、私があなたの前にいる。
この現前する私は、演劇なのか現実なのか、究極のところあなたには区別が付かない。
ところが映画はそうはいかない。
機械を通し、しかも二次元の表現である映画は、これが現実ですと言い張ることもごまかすこともできない。
ところが二〇世紀の演劇は何を勘違いしたのかリアリティの方は映画·映像に任せてしまっ
て、もっぱら主観的表現に力を注いできた。
そしてこの主観的表現を、近代=客観を超克する
「現代演劇」だと考えてきた。
だが、どうもこれは間違っていたのではないか。
そしていまも、この間違いが継続され、信じられているのではないか。
前衛と呼ばれてきた多くの演劇もまた、近代以前の古典回帰に過ぎなかったのではないかと私には思える。
私は「私はこのように世界を認識している」という一つの典型を示したいと書いた。
これは一つの主観的表現である。
しかし、大事なことは、この表現が真善美の価値観からいったん離れて,世界の本質へと迫ろうとするものだという点である。
先ほどの系列図に、私はもう一つの系列を書き足そう。
主観の系列(前近代) 作為→主観→嘘→(神)
客観の系列(近代) 客観→リアル≠真理
記述の系列(現代) 無為→記述(描写) →世界
もう一度順序だてて説明をしよう。
近代思想に裏打ちされた近代芸術は、客観性を追い求めた。
客観性こそが「リアル」なものの根源であり、それのみが世界を正しく認識する手段、真理を発見する回路であると信じていた。
しかし近代思想の崩壊とともに、現代の芸術家たちは主観的表現へと回帰していった。
しかしこの回帰は、まさに後退でしかなかった。
それは一時期目新しく、観衆の気を引くかもしれないが、しかしすでに私たちは近代の洗礼を受けている。
作為→主観→嘘という系列もほた、ある種の真理,ある種の理想を求めるイデオロギーを内包していることは、私たちにとって自明のものとなっている。
そこで私は、もう1つの系列を提言しようと思う。
舞台の上にコップがある。
これは紛れもなくコップなのだから、もうこれ以上何も要らない。
演劇はコップをコップとして見せることだけをすればいい。
コップを直接的に認識し、表現すること。
それが私が考える唯一現代演劇に許された作為である。
そこにはあたかも主観は存在しない。
いや、主観が存在しない表現などというものはありえないのだが、主観は巧妙に隠れ回避される。
それは、パノラマ·メスダッハのだまし絵のように。
ここに私が考える演劇における「無為」がある。
6無為の演劇
私が、演劇は可能かと考えるとき、それは同時に、「無」とは何かということを考えているのだと思う。
仏教では一般に有無の対立を止揚したところに「空」が導き出される。
禅宗ではこの空の境地を「無」の一字をもって表すようだ。
老荘ではこれを無為と呼ぶ。
一方西洋では一般に「無」は右の対立概念、マイナスの意味しかない。
無に価値を見いだすのは、東洋思想に共通の大きな特徴のように思える。
「無」というのは一つの状態で、だからその状態だけを描くこと(記述すること)ができればそれでいい。
行為を描く演劇から、状態を描く演劇へ、ここにまず、発想の転換の第一点がある。
私が考える無為とは、徹底した作為を繰り広げることで、主観性を周到に隠ぺいするということだ。
無為とは何もしないことではない。
老子は言う。
「道は常に為すなくして為さざるなし」と。
ただ、ここで重要なことは、作為は決して主観のために奉仕するのではなく、世界を直接
的に描写するために用いられるという点だ。
そしてその結果は、嘘とか、リアルという観客の解釈の範疇を超えて、ダイレクトに世界へと結びつかなくてはならない。
観客の側も、ダイレクトにその描写された世界と立ち向かわなければならない。
簡単な説明を試みてみよう。
例えば、役者が机を指して「これは机だ」と語る。
これは観客に理解される。
机は机だ。
コツプはコップだ。
異論はない。
もちろん厳密には、絶対的真理を否定する現代思想の立場からいえば、机が机である根拠はもはや崩れてしまっているのだが、しかしそれでも、たぶん21世紀くらいまでは、このくらいのレベルのコミュニケーションは可能だろう。
演劇は哲学ではないからそれで充外だ。ざまあみろ、哲学者たち。
では次に私は歯が痛い」と役者誓う。
ところが、これを観客に納得、共感させるのは私は無理だと思う。
「これは机だ」という命題と私は歯が痛い」という命題は明らかに違う。
「私は歯が痛い」という主観的命題は、どうやっても証明不可能だからだ。
人はそれを聞いて言うだろう。
「ああ、そうですか」と。
従来の演劇は、この私は歯が痛い」という命題を観客に納得させる役者をいい役者と呼んだ。
役者はしゃかりきになって「私は歯が痛いんだ」と叫んだ。
しかし、いかにうまい役者が語ろうとも、いかに大きな声で叫ぼうとも、現代演劇の観客は決してこの台詞に納得はしない。
それは、この命題そのものが「あぁ、そうですか」としか答えようのない類の主観的なものだからだ。
私は、このような命題をテキストに書くこと自体が間違っているのだと考える。
このことに関しては、近代演劇も、現在「現代演劇」と称されている演劇も、劇構造においては同質であると私は思う。
日本の六○年代以降の演劇は役者をテキストから解放したといわれているらしいが、私はそうは思わない。
少なくとも私は歯が痛い」という台詞を書いているうちは、役者はテキストから解放されない。
では、かろうじて信じられる命題は何か?
「彼は歯が痛いらしい」
「彼女は歯が痛いようだ」
というのではどうだろう。
もちろん主語は通常省略されるから、実際の台詞では、「歯が痛いんだって」「歯が痛いみたいよ」というようになる。
英語に訳してみるとわかりやすいのだが、これは, It seems thatという構文だ。
「It」でくくって、ものに還元してしまう。
こうして作者の主観性を巧妙に回避していく。
これが、私のだまし絵だ。
観客は、この「もの」をめぐって,想像力を膨らませる。
そこにのみ、作り手と観客の間に出来事が生まれる可能性がある。
7 まとめ
近代演劇でもっとも重要視されてきたのは「心理」や「感情」といった精神的な概念だった。
近代演劇は「行為」を描く表現で、したがってその行為の動機となる精神が重要視されてきた。
しかし私は、行為ではなく状態を描こうとするのであるから、精神はさほど重要ではない。
喜怒哀楽といったレベルの感情のさらに深い部分にある「意識」とでも呼ぶべきもの、そしてその意識と他者との関係こそが、私が描きたいものだ。
花がある。
その花を見る 摘むf愛するしといった行為を描きたいとは思わない。
できうるなら、花があり人がいる、そこに関係が生まれる。
世界が在る。
それだけの芝居を創りたい。
私が目指す演劇はそこにある。
そこで、ともかくも具体的な手順として、精神的な概念を捨ててそこで、言葉やものといったできるだけ具体的な事物に寄り添って演劇を作るところから、私は作業を始めようと考えている。
これまでの議論を再度、非常にわかりやすく説明してしまえば、演劇で主義主張をするのはやめましょう。
ただ人間や世界のあるがままの姿を、できるだけ分析的に写し出しましょう。
そして、そのことについてみんなで考えましょう。
といったことになると思う。
私は、もしも演劇が可能であるとするならば、この方向以外にないと考えている。
もう一度言うが、もちろん私は、主観性を完全に否定しているわけではない。
芸術が人間の行なうものである以上、それは主観性から逃れられない。
だからこそ、できる限り徹底して、主観性を取り除く努力をし、あるいはそれを巧妙に回避する技術を築き上げていこうではないかと提言しているのだ。
そしてこのことを、もっともわかりにくく説明しようとすれば、ヴィトゲンシュタインの『論理哲学論考』の最終節から言葉を借りて、その「哲学」とされている部分を「演劇」と置き換えて以下のように記してみよう。
演劇の正しい方法とは本来、次のごときものであろう。
演技しうるもの以外なにも演技せぬこと。
故に自然科学(肉体を含めた物体)の命題以外何も演じぬこと。
ゆえに演劇となんのかかわりももたぬものしか演じぬこと。
そして他の人が形而上学的な事柄を演じようとするたびごとに、君は自分の命題の中で,
あるまったく意義を持たない記号を使っていると指摘してやること。
この方法はその人の意にそぐわないであろうし、彼は演劇をしている気がしないであろうが,にもかかわらず,これこそが唯一の厳正な方法であると思われる。
まずは、私の考える演劇の総体については、いったんここまでで止めておこうと思う。
私の理論は、総体が先にあるというよりは、これから語る各論が積み重なって、一つの全体像を形成するものだからだ。
さて私たちは、「無為の演劇」「無の表現」とでも呼ぶべきものに向かって、いかなる作業を進めていけばいいだろう。
まず私は、演劇の大きな特徴である言葉を手がかりにそこに近づいていこうと思う。
私たちが日常使用している日本語の話し言葉をいま一度演劇の側面から考察することから、私の作業を始めようと思う。