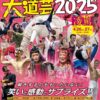Howie Lee ハウイー・リー
―STUDIOVOICE September 2018
Howie Lee
アジアのエレクトロニック·ミュージック·シーンを代表するプロデューサー、Howie Lee (ハウイー·リー)。
かつてイギリスで最先端のUKベース·ミュージックに触れた彼はそれをみずからの国でいかにアップデートし、提示するかに挑戦しつづけてきた。
ハウイーの生みだしたレーベル<Do Hits>はやがて東アジア全体へと広がり、いまや世界中からその動向が注視されている。
「アジアの音楽」という自問のさきで、はたして彼は何を見据えているのか。
「ゴミ」から取り出した欧米の音楽
北京中心地からクルマで1時間半。緑に囲まれた閑静な住宅街のなかに、彼の自宅はあった。
セキュリティチェックを通ってゲートをくぐり、指定された建物を探していると遠くから奇妙なモーター音が聞こえてくる。
音のするほうに目をやると,セグウェイのような電動立ち乗り二輪車に乗った男がこちらに近づいてくるのが見えた。
中国エレクトロニック·ミュージック·シーンにおける最重要レーベル(Do Hits)の主宰者であり、プロデューサーとしても数多くの独創的な作品を発表し続ける鬼才、ハウィー·リー。
オリエンタルなサウンドを取り入れた彼の楽曲はオルタナティブなベース·ミュージックのあり方を示し、アジアのアンダーグラウンドに新たな可能性を切り開いた。
「アメリカンな家でしょう? アイ·アム·アメリカンだからね」。
ハウィーはどこまで皮肉が混じっているのかわからないジョークを飛ばしながら、たしかに欧米風のつくりをした自宅のなかに入ってゆく。
かつて台湾に持っていた拠点を引き払った彼は、北京の喧騒から少し離れたこの地でいまは制作に集中しているのだという。
地上2階、地下1階の豪勢なこの建物は、彼のスタジオを兼ねてもいた。
彼のパートナーであり、<Do Hits>のアートワークを数多く手がけるアーティストでもあるヴィッキーと挨拶をすませて階下のスタジオに向かうと、そこにはさまざまな機材が並んでいた。
これからインタビューを始めるというのに、サンプラーから和太鼓の音を鳴らして遊びはじめるハウィー。
その姿はチャーミングだったが、どこかこちらの様子を伺っているようでもあった。
―ドラムにキーボードにギター 二胡みたいな楽器もある。
立派なスタジオですね。
Howie Lee (以下、HL)なんなら一緒にセッションしましょうか?
―いや、遠慮しておきます(笑)。
それにしてもすごい量の機材ですね。
昔はバンド活動もされていたんですよね?
HL そうですね。13、14歳の頃にギターを始めたのがきっかけでした。
もっとも、音楽が好きで始めたというよりはモテたかったからなんですけど。
ギターを弾けば彼女ができると 言われてね。
―ありがちな話ですね じゃあ、当時は作曲にも興味はなかったんですか?
HL でも、6歳のころにキーボードを習わされていたから、何となくコードとかは知っていたし、興味もありました。
実際に作るようになったのは、15歳のころです。
ベースを弾いてるクラスメイトの女の子の家に行ったら、彼女のパソコンのなかに「Fruity Loops 」ってソフトが入っていたんです。
それを見て、コンピューターで音楽を作れることを知りました。
―では作曲にも若いころから取り組んでいらっしゃったんですね。
音楽も当時から熱心に聴かれていたんでしょうか。
HL いや、聴いてはいたんですが、あまり意識的に聴いているわけではなかったと思います。
ギターを弾くようになってようやくロックンロ-ルがどんなものなのか知ったというか。
当時はニルヴァーナとか、ロックバンドをよく聴いていましたね。
中国には壊れたCDやカセットテープがあって、それを買って聴いていたんですよ。
―壊れたCDやカセットテープ?
HL 言ってしまえば、ゴミですね(笑)。
中国はアメリカから輸入したプラスチックのゴミを処理していて、そのなかには穴
の空いたCDとか切断されたカセットテープがたくさん混じっていたんです。
自分たちはそれを直して聴いていたってわけ。
バラバラになっていても、ちゃんとつなぎ合わせれば聴けるようになるでしょ?
いい匂いがするんですよね(笑)。
当時は正規の輸入盤なんて中国には入ってこなかったから、そういう「ゴミ」を聴いて育ったんです。
それが中国の外で作まられた音楽を聴く唯一の手段でしたね。
ゴミから西 洋の音楽を学んだんですよ。
–すごい話ですね……それで色々な音楽の存在を知った、と。
HL アンダーグラウンドな文化だから、知らない人もいっぱいいると思いますけどね。
当時は正規品が入ってくるような台湾の人びとよりたくさんの音楽を聴けていたんじゃないかな。
しかも、ゴミはキロ単位でまとめ買いできて安いから、たくさん手に入るんですよ。
それに、アメリカでも意外とすぐに捨てられていたのか、「リリース時期」もそこまでズレているわけじゃなかった(笑)。
当時はそうやって新しい音楽を聴いていた人たちがいたんです。



(Do Hits)の誕生とクラブシーンへの参入
―その後は中国伝媒大学に入って、オーディオ·エンジニアリングを学ばれていたんですよね。
大学でも音楽制作を続けられていたんですか?
HL 作ってはいたけれど、自分が所属していたバンドの活動のほうがメインでした。
グリーン·デイみたいなポップパンク·バンドに入っていて。
大学のなかではけっこう人気があって、1000人くらいの大学生のまえで演奏したこともあります。
卒業後に台湾のレーベルから声がかかったんですけど、台湾に行きたいわけでもなかったしそのバンドは辞めることにしたんです。
結局彼らはあまり成功しなかったみたいですけどね。
いま軸足を置いているクラブシーンとはまったくべつのところで活動していたんですね。
HL 北京にクラブがあるのは知っていましたけど、バンドの世界にいましたからね。
DJをするようになったのは、「School Bar」ができてからじゃないかなあ。
―「School Bar」ってなんですか?
HL 友だちのビリーが作ったバーのことです。いまでも北京にありますよ。
そこに来ていたのはロック畑の人ばかりで、エレクトロニック·ミュージックが好きな人はぜんぜんいませんでしたけどね。
最初の1年くらいは調子がよかったんですが、徐たお客さんも少なくなってしまった。
パンク·クラブだったのがよくなかったのかな。
School Barのオーナーは3人いたんですけど、ビリー以外の2人はバンドが演奏するようなロックバーにしたいと言っていて。
でもビリーはダンス·ミュージックが好きだったから、僕たちは「Dada 」という新しくできたバーに移ることにしたんです。
2011から2012年のあいだくらいだったかな。
Dadaはオルタナティブなダンス·ミュージックに力を入れていたから、そちらのほうが性に合っていた。
11人Do Hits)が発足したのもそのころですよね?
―(Do Hits)もビリーと一緒に始めたんです。
当時すでに上海にはエレクトロニック·ミュージックのシーンができていました。
でも、どれも西洋から借りてきたようなものばかりだったから、どうしてもローカルなものが作りたくて。
それでパーティを始めようとビリーが言いはじめて、SulumiやGuzz といったアーティストと一緒に4人で(Do Hits)を立ちあげました。
この名前はLCDサウンドシステムの「You Wanted A Hit」という曲からとったものです。
始めたころはまだSchool Barにいて、途中からDadaに移ったことを覚えています。
エレクトロニック·ミュージックのなかでもダブステップをよくかけるようになって、そのあとさらにベース·ミュージックへとシフトしていった。
いまはもっと実験的な感じになってますけどね。
いまでは専らレーベルとして知られる(Do Hits)だが、2011年の発足から最初の音源リリースまではじつに4年の歳月を要している School Barを拠点としていた時期こそその動きは目立たなかったが、2012年のDadaオープン以降徐々に活動は本格化。
ときにはLAのビートメイカー、マイク·ガオなど海外アーティストも招聘してパーティを続けながら、自分たちの作るべきサウンドを模索していった。
2014年には北京出身のプロデューサー、ジェイソン.フーが参画し、ますますその活動は加速する。
(Do Hits)のパーティのかたわら、ハウィーが海外のイベントに招聘される機会も増えはじめた。2015年3月にはアメリカ·オースティンで開催される国際的フェスティバル「SXSW」への出演も果たし、活躍の幅を広げてゆく。
こうして自分たちのスタイルに磨きをかけた末、2015年6月にリリースされたのが初のレーベル·コンピレーション[Do Hits Vol. 1』だ。
ハウィーやGuzzをはじめ計5人のアーティストが名を連ね、「Made in China」を標榜するサウンドを提示。
さらに同年、彼らは8月、11月と立て続けに新たなコンピレーションをリリースした。
枚数を重ねるたびに台湾のDJ/プロデューサー、ソニア·カリコや成都を拠点とするイギリス生まれのプロデューサー、ハリキリ冞 など数多くの新たなアーティストを巻き込みながら、彼らはレーベルの色ともいえるベース·サウンドを確立してゆく。
それにしても、《Do Hits)はなぜこんなにも急速に成長したのだろうか? じつはこうした活動の本格化は、ハウィーのイギリス留学によって引き起こされたものだったのだという。
なぜ海外のカルチャーを真似る必要があるのか?
ただ、その後あなたがイギリスのロンドン·カレッジ·オブ·コミュニケーションへ留学していたことで(Do Hits)の活動もしばらく止まってしまいますよね。イギリスはいかがでしたか?
HL イギリスではサウンドアートの勉強をしてました。
最初はすごく大変でしたね。
でも、自分にとってはすごく重要な体験になったと思います。
イギリスへ行くまえからエレクトロニック·ミュージックを作ってはいましたが、それがどんな音楽なのかまったく理解していなかったんです。
イギリスの音楽は好きだったけど、なんで自分がここにいるのかわからなかったし、どうやってその音楽に関与すればいいかわからなかった。
そもそもイギリスのシーンに関わるべきなのかどうかさえもね。
どうしてこの音楽に影響されたんだろう?
自分がやっているパーティは一体なんなんだろう? という気持ちがずっとありました。
さらに言えば、プロデューサーって存在が何者なのか、自分が何をしているのかも知りたかった。
でもイギリスに行ってみて、全部同じだと気づきました。
それまで私はその国のカルチャーを崇拝していたんですけど。
結局、みんなパソコンとにらめっこして音楽を作って、クラブでそれをプレイしてるだけ。
もっとも、イギリスのほうが文化的には成熟しているというのは事実です。
―中国もイギリスも同じなんだ、と。
HL そうですね。
でも、同時にこう思ったんです。
なぜ私たちはこの国のカルチャーを真似しないといけないんだろう?と。
なぜ中国にイギリスのベース·ミュージックが必要なのか?
なぜ中国にヒップホップが必要なのか?
なぜ自分たちでほかのことをやらないのか? と。
自分たちで新しいことを始めないといけないということですか?
HL そうです。
もちろん、イギリスの文化はものすごくリスペクトしているけれど、それは彼らの世界であって、私たちのものじゃない。
だから、中国に戻ってから(Do Hits)の活動にも力を入れるようになりました。
たくさんパーティを開いて、どんどん友だちも増えていった。
パーティはコミュニティみたいなものだと思っていましたから。
人を紹介する場でもあるし、私たちみたいなプロデューサーが外に出ていく機会を作りたかった。
レーベルとして楽曲をリリースするようになったのも、中国に戻ってきてからのことです。
中国もイギリスも一緒
―(Do Hits)の活動を広げてみて、周りの反応はいかがでしたか?
HL 反応はすごくよかった。
私たちはそれまでの中国の人びととは違うことを始めていましたから。
でも、それは必ずしも新しいことってわけでもありません。
つねにクールな人たちは中国にいましたから。
―それまでも存在していた中国の文化を提示したわけですね。
こうしてあなたが(Do Hits)を通じて発信するようになった音楽は、「東洋的」とか「中国的」と表現されることも多いように思います。
HL 伝統的な音楽にせよポップカルチャーにせよ、何を取り入れるかはどうでもよくて、とにかくイギリスとは違う何かを作らなくちゃいけないと思っていました。
イギリスのものをサンプリングして作った音楽をかけても、誰も興味を持ってくれないんですから。
シンプルな話じゃないですか?
私たちは中国のなかですごく西洋化されてきた人間で、かつては自分たちのカルチャーのほうが低俗なものだと思っていた。
でも、イギリスに行ってみて、全部一緒だと気づいて。
ポップカルチャーなんてどこも俗っぽくて、どこも退屈。
テレビCMみたいにね。
だから(Do Hits)もテレビCMなんです。
私たちDJはセールスマンで、かつて外国の音楽を売っていた。
でもいまは自分の国の音楽を売らなきゃいけない。
そっちのほうが売れるとわかってますからね。
―マーケティングみたいな発想に近いんでしょうか。
HL マーケティング戦略に近いかもしれませんね。
だからオリエンタリズムとは違うと思っているし、べつに伝統的なものを使っているわけでもない。
「中国の人びとがよく知っているもの」って感じでしょうか。
海外からたくさんの人が(Do Hits)のパーティに来て、ショックを受けるわけです。
そこにいる中国の人びとは私がかける曲を知っているし、何をしているかもわかってる。
でも、彼らはわからないから「この音楽は何なんだ!?」と驚く。
それで、家に帰ってから、もっと中国の文化を調べるようになるんですよ。
―おもしろい考え方ですね。
でも、あなたのそういう考えは中国のリスナーに伝わっているものなんでしょうか?
私が作る音楽が一体なんなのか、多くの人には理解してもらえていないと思うんですが、彼らはみんなパーティに来てくれるんです。
そして熱狂してくれて、クラブから離れることがない。
人びとがクラブに来て「ああ、西洋のカルチャーだよね」なんて思われるようになるのが嫌なんですよ。
でも、(Do Hits)のパーティに来て、そこで生まれているグルーヴを感じている人はそういうことを言わない。
この人はすべて中国の曲をかけるから、ここは違うクラブなんだなと理解してくれる。
そうすることで、私自身もその場所に居られる気がしてくるんです。
ハウィーや(Do Hits)らの動きと共鳴するようにして、近年世界の音楽市場におけるアジアのプレゼンスは急速に向上している。
なかでも大きな要因のひとつといえるのは、2015年に日系アメリカ人のショーン·ミヤシロが立ちあげたメディア·プラットフォーム(88rising)の存在だろう。
長らくアジアのヒップホップを注視していたミヤシロは(88rising)のYouTubeチャンネルを通じて韓国のキース·エィプや中国のハイヤー·ブラザーズなどさまざまなラッパーを紹介。
プラットフォームを横断しながらオルタナティブなアジアのカルチャーを提示し、2017年にはハイヤー·ブラザーズら各国のアーティストを引き連れたアジアツアーも成功させている。
YouTubeで数百万回再生される動画を発信し続ける(88ris-ing)と、アンダーグラウンドなエレクトロニック·ミュージック·シーンで着実に影響力を増してきた(Do Hits)”同時多発的に成長してきた彼らの取り組みは、平行線を描くようでありながらじつは交差していた。
その交点に立っていたのが、ほかでもないハウィーだった。
しかし、いまやハウィーは(88rising)的なアジアの盛りあがりとも、(Do Hits)的なアジア独自のベース·ミュージックの醸成とも少しずつ距離をとろうとしていた。
北京郊外のスタジオで自分と向きあいながら創作に没頭するハウィーから、アジアの隆盛はどう見えているのだろうか。
孤独と向きあうこと
中国の音楽という点では、いま(88t-sing)などを通じて中国のヒップホップが注目されていますよね。
HL ハイヤー·ブラザーズが(88rising)に取りあげられたのは、私が「Boiler Room」で彼らの曲をかけたのがきっかけでした。
いまはボハン·フェニックスのマネージャーをしてるアリソン·トイがBoiler Roomでかけた曲を聴いて連絡をくれて、ハイヤー·ブラザーズとつないだんです。
そこから先はご存知のとおり。
もっとも、私はそこから何か利益を得たわけじゃないですけどね(笑)。
―中国や韓国のヒップホップが世界的に注目を集めている現状を、どう捉えていらっしゃいますか?
HL ヒップホップは大好きですよ!でも、私はラッパーじゃありませんからね。
ヒップホップのような道だけが成りあがるルートではないですし、私は自分自身の仕事をするだけです。
そもそも彼らと同じようにトップを目指しているわけでもないですから。
でも、トラックメイキングの依頼はたくさん届きますよ。
ただ、私が実際にプロデュースしたのはポハン·フェニックスの『FOREIGN EP』だけです。
最近は私の音楽も変わってきてしまったし、ビートメイカーとして活動していきたいわけでもないので、正直興味がないんですよね。
それにあまりにもたくさんの人がアプローチしてきて、かなり疲れてきてしまったんで
す。
いまは音楽で大儲けしたいわけではないし、自分の作ったもので幸せになれたらいいなという感じです。
―なるほど。では、いまほかに注目されている音楽はありますか?
最近は中国のフォーキーな音楽をよく聴いています。
古いものではなくて、リー·ダイグオやファン·キンのような現代のアーティストがいいですね。
最近はクラブ.ミュージックも苦手になってしまって トゥーマッチというか。
(Do Hits)の活動もちょっと限界を感じてきていますね。
―中国のクラブシーンにもあまり興味がなくなってしまったんですね。
HL いまは北京のシーンに軸足を置いていないですからね。
北京に拠点があるわけでもないし、(Do Hits)のムーブメントは終わってしまったんだと思います。
7月の終わりに上海でライプをするんですが、(Do Hits)としてはそれが最後のショーケースになるかもしれません。
―それは残念です。今後はどうされるつもりなんでしょうか?
HL レーベルのことではなくて、自分の活動に力を入れたと思っています。
プロデューサーになりたてのころは自分を出すのが恥ずかしかったんですが、作品を作ったりパフォーマンスを重ねたりすることでそういう気持ちはなくなりました。
いまはもっと実験的なパフォーマンスに興味がありますね。
―新しい局面に突入しようとしているわけですね。お話を伺っていて、環境の変化も大きいのかなと感じました。
HL 少しまえまで台北に2年間住んでいたんですが、都会に住むのが嫌いになってしまって。
すごくうるさいし、それもあって都会的な音楽にもうんざりしてきているんです。
だからいまは郊外に住んでいます。
ライフスタイルも変えて、最近は朝方になりましたからね。
朝6時に起きたり(笑)。
朝に作業するのはいいですよ。
もちろん、新たな出会いにも興味はあります。
この時代において、コミュニティの存在は偉大ですから。
でも、孤独であることも同じくらい大切なことじゃないですか?
自分自身とどう向きあうかがどんどん重要になっていくと思っています。
新しい人びとに出会うまでは、自分自身の時間を楽しんでおきたいんです。